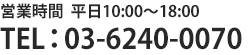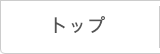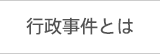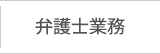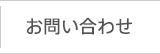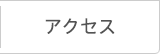|
≪遺言能力≫遺言については、前提として遺言能力が必要です。能力として似たものとして、成年後見の場合に問題とされる「行為能力」というものがありますが、遺言はそこまでの能力がなくてもできるとされています。問題となるのは、高齢者で判断能力に疑問がある人の場合です。この場合でも遺言自体はでき、遺言能力があったことを証明できるならば、その遺言は有効なものとなります。ただ、遺言能力自体が争われることが予想されますので、遺言能力が遺言者にあったことを証明できるようにしておく必要があるでしょう。医師(できれば普段から遺言者を診察している主治医がいいでしょう。)に認知症を判断する際に用いるテストをしてもらったうえで遺言できるだけの判断能力があったことを診断してもらい、診断書をもらっておくことなどが考えられます。逆に遺言能力がない遺言者の遺言は無効です。 ≪遺言の方式≫遺言はどのように作成すればよいのでしょうか。一般的には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言という方式のどれかによることになります。ではこれらはどう違うのでしょうか。以下の表を参照してください。
以上のようにそれぞれの特質があります。コストをかけたくないならば自筆証書で作成すればいいのですが、内容について公証人等の立ち合いによる保障がないためにその遺言が遺言者の意思であるかを事後的に争われる可能性があります。そして、公正証書遺言以外の遺言については、相続人が発見次第、家庭裁判所での検認をうけなければなりません。この検認手続は遺言者の遺言の存在を確認するためのものであり、遺言内容にかかわるものではありません。遺言内容を争うときは、遺言の有効無効を訴訟等で争う必要があります。 手続的にはコストがかかったりすることなどの負担がありますが、検認などの手続を受けず遺言者の遺言とできる点で遺言を作成する場合には公正証書遺言が無難と言えます。 ただし、先に述べた通り、遺言内容の有効無効についてはどの方式をとっても確保されるものではありません。 ≪遺言作成の際の注意≫遺言は、遺言者(故人)の意思を実現する最後の手段です。しかし、無制限にできるわけではありません。一番問題になるのが相続人の遺留分です。相続人には遺留分と言い、最低限の相続分を認められています。ですので相続人の遺留分に配慮しない遺言(例、相続人の一部のものに全て相続させる遺言、誰かに遺贈する遺言)をすると相続開始後に遺留分をめぐる紛争になることがしばしばです。そこで遺言作成の際に、相続人の遺留分に配慮した遺言内容にする、相続する相続人に他の相続人への遺留分に相当する代償金を払わせる内容にするなどの対策をとることが必要です。 ≪遺言について修正したい場合≫遺言はいつでも撤回できます。また、一度作成した遺言を修正したい場合には、修正した遺言を作成すれば後に作成された遺言が遺言とされます。そして、前後の遺言で内容が抵触する場合には、後の遺言が遺言者の遺言とされることになります。 【関連業務】高齢者問題 >> 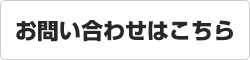
|
|
辻本法律事務所 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目25-4 ベルスクエア本郷3F Tel: 03-6240-0070 / Fax: 03-5689-5353
Copyright © 2015 辻本法律事務所. All Rights Reserved. |