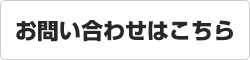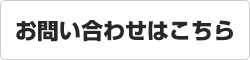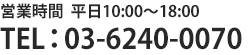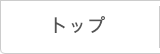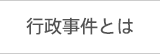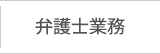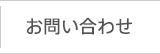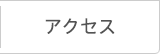介護事業契約と成年後見契約でのトラブルについて
介護事業においては、利用者が認知症等で行為能力がなくなったり、減退するなどして直接の契約当事者として契約等できなくなる場合があります。その場合、通常成年後見人(後見人、保佐人、補助人)が選任され契約することになります。
成年後見等がされている場合、利用者を代理して成年後見人が介護利用契約を結びます。ただ、事業者の介護利用契約書を拝見しますと、しばしば代理人として成年後見人が契約することを想定していないものが多いように思われます。この場合、契約できなかったり、契約書としての問題点を後になって指摘されるなどのトラブルとなりかねません。
まず、介護利用契約においては、たとえば老人ホームの場合で言うと、「入居者(利用者)」「見元引受人」「連帯保証人」という当事者が考えられます。成年後見人等はどの立場となるのでしょうか。
第一に考えなくてはならないのは、成年後見人等はあくまで入居者本人の代理人として本人の財産管理を行います。成年後見人が介護利用料金等を自らの資産で支払ったり、負担することはありえません。あくまで入居者本人の資産等を管理する中で本人の資産から利用料等の支払をすればよいだけです。ですので、成年後見人が自らの資産等で債務を負うことになる「連帯保証人」ではありません。
次に「身元引受人」はどうでしょうか。身元引受人については明確な根拠とすべき法規定等はありません。一般的には、利用者が死亡した場合や退去する場合の身柄引受けをしたり、急病等の緊急時対応などをする立場が身元引受です。この内容であれば、成年後見人等は本人の身上監護をするのですから問題ありません。問題となるのは、身元引受人でありながら利用者の債務を連帯保証(連帯)したりする場合です。先に述べたように成年後見人等はあくまで本人の財産管理の一環として、本人の資産内で必要な債務の負担を本人を代理して行うのであり、自らが債務を負担することはありません。
ですが、しばしば介護利用契約書で身元引受人が本人の債務を連帯保証する旨の規定が入っています。成年後見人等は自らが債務を負担することはないので、連帯保証や連帯債務を負うことはないため、このような「身元引受人」にはなれません。ここに問題があるのです。しばしば拝見しますが、定型の介護利用契約書では、入居者(利用者)になるか、連帯保証債務を負う「身元引受人」しかないため、成年後見人等が契約できないことになってしまいます。
結局は、入居者(利用者)でもなく、連帯保証を負うような身元引受人にはなれず、連帯保証人でもないのです。あくまで入居者の代理人なので利用者としての契約を結ぶようにしなくてはならないのです。
介護利用契約では、認知症などによる成年後見の利用が想定されていながら成年後見人等に連帯保証(連帯債務)を負う身元引受人としての契約をさせることとなり、必要以上の債務が成年後見人に負わせることとなってしまうのです。成年後見人等がそれを理解したうえで身元引受人として契約するならば相手が了解しているので良いのですが、了解等のない場合や知識が十分にないために身元引受人として連帯保証を負う契約を結ばせるような場合には、利用契約ができなくなってしまったり、契約した後にトラブルになってしまうことにもなりかねません。実際、利用者の側(成年後見人)で契約書の修正要望をしたこともありますし、介護事業者の側で利用契約書の修正のアドバイスをしたこともあります。
ですので、成年後見人等が契約する場合を想定し、代理人等としての契約ができるように契約書を準備しておくことが重要です。介護事業契約者におかれては、御社の介護利用契約書を確認し、成年後見人等が契約する場合に備えた契約内容になっているのかを一度チェックしてみることをお勧めします。対応できていない場合には、契約書を改定することをお勧めします。
【関連業務】企業法務 >>