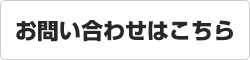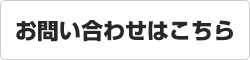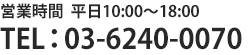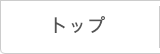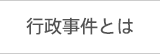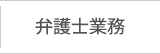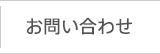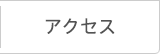参考例(定型フォーマット)の契約書の問題点
事業者の方は事業を進める上で様々な契約をしていることと思います。そして、多くの場合には契約書を最初から作成するのではなく、所轄官庁や役所などが案内した参考例(いわゆる定型書式)を用いていることが多いことと思います。もしくはインターネットで契約書のフォーマットとなりそうな参考例を少し直して用いているかもしれません。
最初から自分の事業に沿った一般的な契約書を作成するのは時間もかかりますので、定型書式を用いるのは一番手間が少ない方法です。ただ、事業内容に沿わないにもかかわらず、そのまま定型書式を用いて放置し、実情に合わない契約書を修正しておかなかったために後で大きな問題となることが少なくありません。例えば、実施していないサービス内容を残しているために後で問題が発生する場合などがあります。実施していないサービスについての記載が契約書にあると、当然、利用者に対し契約書内容のサービスをする合意をしていることになり、サービスが提供できないことは債務不履行となります。結果、利用者からクレームを受けたり、利用解除されたり、場合によっては損害賠償を請求されたりすることになります。
実際、当事務所へのご相談で、自社で提供していないサービスについてのクレームをつけられて困っているというものがありました。契約書を確認すると確かに提供サービス内容として記載されているために修正や謝罪等の対応をせざるを得なかったことがあります。
また、他にも、利用代金の未払などによる解除についての定め(どれくらいの未納で解除できるのか、解除する場合の手続)が明確にされていなかったために、事業者側で解除等の手続をとりたいのだがどうしたらよいのかの判断に困ってしまったケースなどがありました。
このようなことから、定型書式を用いる場合にはこのようなリスクが潜んでいることをご理解した上で利用いただくか、もしくは時間と手間がかかりますが、自社の事業の実情にあっているのか一度細かく見直すことをお勧めします。
【関連業務】企業法務 >>