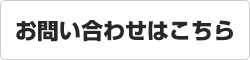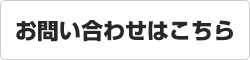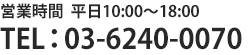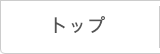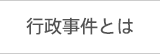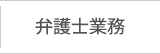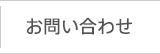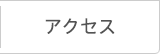遺言については、遺言の記事で記載したように公正証書の形で作成する「公正証書遺言」(民法969条)とその形をとらないでする「自筆証書遺言」(民法968条)、それ以外に公証人や証人とともに封をする形で行う「秘密証書遺言」(民法970条)があります。
遺言内容について、自分の遺言であることについての争いをなくしておくためには、公証人が証明してくれる公正証書遺言を使うのがよいです。
ただ、公証人に遺言を作成してもらうなど手続が面倒と感じたり、費用がかかって利用しにくいと感じるために、公正証書遺言を使わず遺言を残したいということがあると思います。その場合、法的には先にお話した3種類しかないため、法的に有効な遺言とするには自筆証書遺言の形として出来ていなければなりません。自筆証書遺言は簡単な方法で作成する遺言ですが、最低限の形式を満たしていない限り自筆証書遺言としても認められず、法的に遺言として扱ってもらうことはできません。ですので、遺言(自筆証書遺言)を残しておこうという場合には以下の点に注意してください。
(1)遺言内容、日付、氏名について自書すること。
(2)押印をすること。
これらの要件は最低限の要件で、これを満たさないと自筆証書遺言としても認められません。ですので、パソコン等で遺言内容を印字しておいても自書していないため、法的に有効な「遺言」とはなりませんので注意してください。
ただ、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合、目録だけは自書しないでもよいとされました(968条2項)。この場合は、作成した目録の毎葉に署名押印しなくてはなりません。
そして、内容等についての加除修正・変更をする場合には、訂正変更箇所への押印をする必要があります(968条3項)。
せっかくの自分の意思を残そうとした場合に、形式的なことで「遺言」と扱われないならば勿体ないので、最低限の形式だけは満たすように作成するように注意してください。
【関連業務】高齢者問題 >>